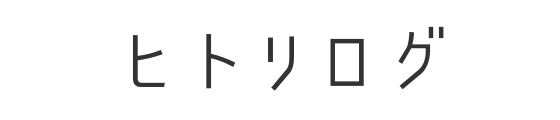一人暮らしでスーパーが遠いというのは、日々の生活にじわじわと影響を与える、地味にきつい問題ですよね。
一人暮らしの理想のスーパーの距離は徒歩10分圏内と言われています。しかし、現実には、近いようでも毎日の往復が地味にしんどい…。特に車を持たない大学生や高齢者の場合、重い荷物を徒歩で運ぶのは本当に大変です。中には、田舎暮らしで徒歩30分、2キロ以上離れているケースも。
この記事では、そんな一人暮らしでスーパーまでの距離が遠いという悩みを解決するためのヒントを紹介します。スーパーまでの理想の距離から、遠い場合の具体的な対策、さらには物件選びで失敗しないためのチェックポイント、逆に近い場合のデメリットまで、あらゆる情報を網羅しました。
今の生活を快適にするヒントが、きっと見つかるでしょう。
- 一人暮らしのスーパーまでの理想的な距離の目安
- スーパーが遠い場合の具体的な解決策
- 重い荷物を運ぶ負担を減らすための工夫
- 物件選びで後悔しないためのチェックポイント
一人暮らしでスーパーの距離が遠いときの悩みと現状
一人暮らしでスーパーが遠いというのは、日々の生活の質に直接影響する深刻な問題です。特に、車を持っていない場合はその負担がさらに増大します。
食料品や日用品の買い出しは、生活に欠かせないルーティン。しかし、そのたびに時間と労力を大きく削られてしまうと、せっかくの一人暮らしの楽しさも半減してしまいますよね。
この章では、一人暮らしでスーパーまでの距離がどれくらいだと遠いと感じるのか、理想と現実のギャップ、そしてそれが生活にどのような影響を及ぼすのかを、様々な視点から掘り下げていきます。
- スーパーまでの距離の平均は徒歩何分?10分以内が理想?
- スーパーまで徒歩30分、2キロ以上離れているとどうなる?
- 田舎は車移動前提?都市部とのスーパーまでの距離の違い
- 大学生はスーパー・駅・学校の近さどれが大事?
- 徒歩圏内にスーパーがないと老後・高齢者はきつい?
- 逆にスーパーが近いデメリットはある?意外な落とし穴
スーパーまでの距離の平均は徒歩何分?10分以内が理想?
「みんな、どれくらいの距離のスーパーに通っているんだろう?」と気になるかもしれません。スーパーマーケットまでの距離に関する全国的な平均データは一概には言えませんが、多くの人が「徒歩10分圏内」を一つの目安としているようです。
例えば、一般社団法人全国スーパーマーケット協会の「2018年版 スーパーマーケット白書」によると、自宅からスーパーまでのアクセス時間は、交通手段が徒歩の場合は5分以内と回答した人が54.5%で、6~10分以内が27.3%という結果でした。
また、徒歩以外の交通手段も含まれますが、農林水産省が2016年に行った調査では、食料品の買い物でよく利用するお店までの片道の所要時間は、5分以上10分未満と回答した人が36.2%で最も多く、10分以上15分未満が26.8%、5分未満が13.2%でした。
参考:農林水産省
物件情報でよく目にする「駅徒歩◯分」という表記。これは不動産公正取引協議会連合会が定めた基準に基づき、「道路距離80mを歩くのにかかる時間を1分」として計算されています。つまり、徒歩10分は約800mの距離を指します。
| 徒歩分数 | 距離の目安 |
|---|---|
| 5分 | 約400m |
| 10分 | 約800m |
| 15分 | 約1,200m |
| 20分 | 約1,600m |
この「徒歩10分」というラインを大幅に超えてしまうと、買い物が「面倒なイベント」になってしまい、食生活の乱れや時間の浪費を招く一因となりかねません。理想を言えば、重い荷物を持っても苦にならない徒歩5分以内にスーパーがあると、生活の利便性は格段に向上すると言えそうです。
スーパーまで徒歩30分、2キロ以上離れているとどうなる?
もしスーパーまで徒歩30分、距離にして約2.4km離れていると、生活はどのように変化するのでしょうか。まず考えられるのは、買い物に行くこと自体が一大イベントになるということです。
往復だけで1時間もの時間を要するため、「ちょっと牛乳を買いに」という気軽な利用は難しくなります。結果として、買い物の頻度が減り、「まとめ買い」が基本スタイルになるでしょう。
しかし、徒歩でのまとめ買いは、持ち運べる量に限界があります。特にお米や飲み物といった重い商品は、購入をためらってしまうかもしれません。夏場の炎天下や冬の寒い日、雨や雪の日には、その負担はより大きいです。食生活が偏り、外食やコンビニ弁当に頼りがちになる可能性も高まります。
田舎は車移動前提?都市部とのスーパーまでの距離の違い
スーパーまでの距離は、住んでいる地域によって大きく異なります。都市部では駅前や住宅街に複数のスーパーが点在し、徒歩圏内で買い物ができる環境が整っていることが多いです。
一方で、郊外や田舎では、大型スーパーが主要な道路沿いに集中している傾向があります。そのため、車での移動が前提となっている地域が少なくありません。
公共交通機関であるバスも、都市部に比べて本数が少なかったり、バス停からスーパーまでさらに歩く必要があったりすることも。田舎暮らしを検討する際は、スーパーまでの物理的な距離だけでなく、そこへ至るまでの交通手段もしっかりと確認することが不可欠です。
このような状況は「買い物難民」や「食料品アクセス問題」といった社会的な課題にもつながっています。近年では、こうした地域での買い物を支援するために、商品を軽トラックに乗せて販売する「移動スーパー」といったサービスも注目されています。
大学生はスーパー・駅・学校の近さどれが大事?
これから一人暮らしを始める大学生にとって、物件選びの優先順位は悩ましい問題です。「大学への通いやすさ」「駅からの近さ」「スーパーの利便性」、どれを最も重視すべきでしょうか。
2018年に東急不動産ホールディングスの学生情報センターが、同社が運営するマンションに入居する学生316人に実施した調査によると、部屋を選ぶ際に重視したほうが良い利便性は「スーパーが近くにある」が76.9%と最も多く、次いで「駅の近く」が67.4%、「学校の近く」が54.7%という結果でした。
参考:株式会社学生情報センター
しかし、どれを最も重視すべきかは、個々のライフスタイルによって変わってきます。
例えば、自炊を頑張りたい人にとっては、スーパーの近さは絶対に譲れない条件でしょう。新鮮な食材を手軽に購入できる環境は、健康的で経済的な食生活の基盤となります。
一方で、アルバイトや遊びなどで帰りが遅くなりがちな人は、駅の近さを優先した方が、夜道を歩く時間が短くなり、防犯面でも安心です。
また、大学での授業や研究が忙しい人であれば、大学への近さが最も重要かもしれません。通学時間を短縮できれば、その分を学習や休息に充てることができます。
| 重視するポイント | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| スーパーの近さ | ・自炊しやすく、食費を節約できる ・健康的な食生活を送りやすい | ・駅や大学から遠くなる可能性がある ・活動範囲が家の近所に偏りがち |
| 駅の近さ | ・通学やアルバイト、遊びに行くのに便利 ・夜道の帰宅が安心 | ・家賃が高くなる傾向がある ・スーパーや大学が遠くなることも |
| 大学の近さ | ・通学時間が短く、朝ゆっくりできる ・忘れ物をしてもすぐに取りに帰れる | ・駅や繁華街から離れている場合がある ・家賃が周辺相場より高いことも |
最終的には、自分の生活の中で何に最も時間と労力をかけたくないかを考えることが、最適な物件選びの鍵となります。
徒歩圏内にスーパーがないと老後・高齢者はきつい?
若い頃は体力でカバーできたスーパーまでの遠い距離も、年齢を重ねると深刻な問題に変わります。高齢者にとって、徒歩圏内にスーパーがない生活は非常に厳しいものと言わざるを得ません。
最大の課題は、身体的な負担の増大です。筋力や体力が低下すると、重い買い物袋を持って長い距離を歩くこと自体が困難になります。雨の日や暑い日には、転倒や熱中症のリスクも高まります。
さらに、多くの高齢者が直面するのが自動車の運転免許の返納です。これまで車で買い物に行っていた人が移動手段を失うと、一気に買い物難民になってしまうケースは少なくありません。バスも本数が少なかったり、バス停から自宅まで距離があったりすると、利用のハードルは高くなります。
農林水産省の推計によると、2020年時点で全国に約904万人もの買い物弱者(店舗まで直線距離で500メートル以上、65歳以上)がいるとされています。65歳以上の全人口の25.6%です。
参考:農林水産省
逆にスーパーが近いデメリットはある?意外な落とし穴
「じゃあ、スーパーはとにかく近ければ近いほど良いんだ!」と思いがちですが、実は近すぎることによるデメリットも存在します。
- 無駄遣いの増加:「すぐそこにある」という手軽さから、必要のないものまでつい買ってしまう「ついで買い」が増え、食費がかさんでしまうことも考えられます。
- 騒音:スーパーの営業中はもちろん、早朝や深夜の商品搬入時のトラックの音や作業音が気になる場合があります。
- 匂いや害虫:惣菜コーナーからの匂いや、ゴミ置き場周辺にゴキブリやハエ、ネズミなどが発生しやすいリスクもあります。
- 人の往来や交通量:買い物客が増える時間帯は、周辺道路が人や車で混雑し、交通渋滞が発生したり、騒がしく感じられたりする可能性があります。
- 路上駐車:スーパーに専用の駐車場がなかったり、あっても常に満車状態だったりすると、周辺道路での路上駐車が問題になることがあります。
- 明るさが気になることも:24時間営業のスーパーだと、夜通し照明がついていて、カーテンを閉めても光が漏れてきて眠りを妨げる…なんてことも考えられます。
これらの問題は、必ずしも起こるわけではありませんが、念のため頭に入れておくと良いでしょう。
一人暮らしでスーパーの距離が遠いときの解決策と工夫
一人暮らしでスーパーが遠いと、日々の買い物が本当に憂鬱になりますよね。しかし、諦めるのはまだ早いです。少しの工夫と便利なサービスの活用で、その「しんどさ」は劇的に改善できます。
この章では、一人暮らしでスーパーとの距離というハンデを乗り越えるための、具体的かつ実践的な解決のヒントを多角的に提案します。移動手段の見直しから、買い物の仕方、便利なサービスの活用まで、自分に合った方法が見つかるかもしれません。
- スーパーが遠くてしんどいときの対策
- 重い荷物を徒歩で運ぶときの負担を減らす方法
- スーパーまでの距離で失敗しない物件選びのポイント
スーパーが遠くてしんどいときの対策
スーパーが遠くて「もう、しんどい…」と感じたとき、まず試してみたい基本的な対策がいくつかあります。大掛かりな準備は不要で、今日からでも始められることばかりです。毎日の負担を少しでも軽くするために、これらの方法を組み合わせて実践してみましょう。
自転車やカーシェアを活用する
徒歩での移動が困難なら、まずは移動手段を確保することを考えましょう。
自転車は、最も手軽で経済的な選択肢の一つです。徒歩30分の距離でも、自転車なら10分程度に短縮できます。電動アシスト自転車であれば、坂道や重い荷物を積んだ帰り道も楽々です。初期投資はかかりますが、日々の移動が格段に快適になります。
もし運転免許を持っているなら、カーシェアリングも有効な選択肢です。月々の固定費が安いサービスも多く、使いたいときに短時間だけ車を借りることができます。お米や飲み物といった重いものをまとめ買いする際に非常に便利です。
買い物頻度を減らす
スーパーに行く回数そのものを減らせば、移動にかかる時間と労力を大幅に節約できます。そのためには、一度の買い物で多くの食材を計画的に購入し、上手に保存・活用するスキルが求められます。
まとめ買いをする
買い物に行く日を「週に1回」や「3日に1回」と決め、まとめ買いを習慣にしましょう。
行く前には、冷蔵庫の中身を確認し、1週間分のおおまかな献立を考えながら買い物リストを作成するのが成功の鍵です。リストがあれば、買い忘れや余計なものの購入を防ぎ、効率的に買い物を済ませることができます。計画性が身につき、結果的に食費の節約にもつながるでしょう。
食材を冷凍保存する
まとめ買いした食材を長持ちさせるには、冷凍保存が欠かせません。肉や魚は小分けにしてラップに包み、野菜はカットしたり下茹でしたりしてから冷凍すると、調理の時短にもなって一石二鳥です。
例えば、ひき肉はそぼろ状に炒めてから、きのこ類は石づきを取ってほぐしてから冷凍用保存袋へ。このように下処理をしておくだけで、平日の料理がぐっと楽になります。
缶詰・レトルト食品を常備する
日持ちする缶詰やレトルト食品は、スーパーが遠い暮らしの強い味方です。サバ缶やツナ缶、トマト缶などは、さまざまな料理に活用できる万能選手。カレーやパスタソースなどのレトルト食品も、疲れて何もしたくない日のためにいくつかストックしておくと安心です。
最近では、栄養バランスに配慮した商品も増えているので、上手に活用しましょう。
買い物場所の選択肢を広げる
「買い物=スーパー」という固定観念を一度リセットしてみましょう。視点を変えれば、意外と身近な場所が買い物の拠点になるかもしれません。
コンビニ・ドラッグストア
最近のコンビニエンスストアは、生鮮食品や冷凍食品の品揃えが充実しています。スーパーに比べると割高なイメージかもしれませんが、少量だけ必要な場合や、急な買い足しには大変便利です。
また、ドラッグストアも、牛乳や卵、パンといった基本的な食料品を扱う店舗が増えています。トイレットペーパーや洗剤などの日用品の購入と合わせて、一度に買い物を済ませられるのが魅力です。
農産物直売所・道の駅
もし郊外や田舎に住んでいるなら、農産物直売所や道の駅をチェックしてみるのもおすすめです。生産者から直接届けられるため、新鮮で旬の野菜や果物が手頃な価格で手に入ることが多いです。
スーパーでは見かけない珍しい品種に出会える楽しみもあります。ただし、営業時間が短い場合もあるため、事前に確認してから訪れることをおすすめします。
便利なサービスを活用する
現代には、物理的な距離のハンデを解消してくれる便利なサービスがたくさんあります。初期設定は少し手間かもしれませんが、一度使い始めれば、その快適さから手放せなくなるはずです。
ネットスーパー
ネットスーパーは、既存のスーパーマーケットがインターネットで注文を受け付け、自宅まで商品を配送してくれるサービスです。注文から最短当日に届けてくれるため、急な需要にも対応できます。
いつも利用しているスーパーの品揃えを、スマホやパソコンから手軽に注文できるのが魅力です。お米や飲料などの重いものも玄関先まで届けてくれるため、買い物の負担が劇的に軽減されます。
食材宅配サービス
食材宅配サービスは、独自の基準で選んだ食材や、半調理済みのミールキットなどを定期的に届けてくれるサービスです。毎週決まった曜日に届くため、買い物の計画が立てやすくなります。
特に、カット済みの野菜と調味料がセットになったミールキットは、献立を考える手間も省け、短時間で本格的な料理が作れるため、忙しい人にぴったりです。
宅配弁当サービス
自炊そのものが負担に感じる場合は、宅配弁当サービスがおすすめです。管理栄養士が監修した栄養バランスの取れたお弁当が、冷凍の状態でまとめて届くサービスが主流です。
電子レンジで温めるだけで、手軽に健康的な食事を摂ることができます。スーパーが遠いという悩みだけでなく、日々の食生活全体の改善にもつながる選択肢です。
重い荷物を徒歩で運ぶときの負担を減らす方法
移動手段がなく、どうしても徒歩で重い荷物を運ばなければならない場面もありますよね。そんな時に、少しでも身体への負担を減らすための工夫をご紹介します。
キャリーカートを活用する
お米やペットボトル飲料、週末のまとめ買いなど、荷物が重くなるときに絶大な効果を発揮するのがキャリーカート(ショッピングカート)です。
車輪が付いているため、重い荷物も楽に運ぶことができます。使わないときはコンパクトに折りたためるタイプや、保冷機能が付いたバッグがセットになっているものなど、様々な種類があります。自分のライフスタイルに合ったものを選ぶと、買い物が格段に楽になるでしょう。
リュックで重心を安定させる
荷物を運ぶ際は、手で持つよりも、リュックサックを使う方が、身体への負担が少なくなります。両肩に重さが均等に分散されるため、片側に負担が偏るのを防ぎ、身体のバランスが安定します。
荷物を詰めるときのコツは、重いものを背中に近い位置に入れること。こうすることで重心が安定し、体感的な重さを軽減することができます。
複数回に分けて買う
一度にたくさんの荷物を持とうとせず、買い物を複数回に分けるというのも一つの手です。例えば、「今日は日用品だけ」「明日は生鮮食品だけ」というように、目的を絞って買い物に行くことで、一回あたりの荷物の量を減らすことができます。
通勤や通学の帰りに少しだけ立ち寄る、というスタイルを習慣にするのも良いでしょう。
重いものは宅配で頼む
「全部を徒歩で運ぶ」と考えるのではなく、重いものやかさばるものだけを別の方法で調達するという発想の転換も重要です。お米や水、調味料、トイレットペーパーといった定番商品は、ネットスーパーや通販サイトを利用して自宅に直接届けてもらうのが賢明です。
生鮮食品など、自分の目で見て選びたいものだけをスーパーで買うようにすれば、徒歩での買い物もずっと身軽になります。
スーパーまでの距離で失敗しない物件選びのポイント
これから一人暮らしを始める、あるいは引っ越しを考えているなら、新居ではスーパーまでの距離で後悔したくないですよね。物件選びの段階でチェックしておくべき重要なポイントを解説します。
内見時に自分の足で歩いてみる
物件探しの際、不動産情報に書かれている「スーパーまで徒歩〇分」という表示を鵜呑みにするのは危険です。この時間は、前述の通り、信号や踏切の待ち時間、坂道などを考慮していません。内見に行く際には、必ず最寄りのスーパーまで自分の足で歩いてみることをおすすめします。
実際に歩いてみることで、地図上ではわからなかった坂道の有無や、信号の多さ、歩道の広さ、街灯の整備状況といった、日々の買い物に影響するリアルな環境がわかります。特に、夜の時間帯の道のりの安全性も確認しておくと、より安心です。
スーパー自体も徹底リサーチする
スーパーが近くにあれば何でも良い、というわけではありません。そのスーパー自体が自分のライフスタイルに合っているかどうかも、非常に重要なポイントです。
- 営業時間: 仕事帰りが遅い人は、深夜まで営業しているか確認しましょう。
- 価格帯: 高級志向なのか、リーズナブルな価格設定なのか。
- 品揃え: お惣菜は充実しているか、好きなメーカーの商品は置いているか。
- 支払い方法: クレジットカードや電子マネーは使えるか。
いくら近くても、価格が高すぎたり、欲しい食材が手に入らなかったり、営業時間が短くて利用しにくかったりしては意味がありません。
スーパー以外の店もチェックする
スーパーだけでなく、その周辺にある他のお店の存在も、暮らしの利便性を左右します。
例えば、ドラッグストアが近くにあれば、日用品や一部の食料品を安く手に入れることができます。100円ショップがあれば、細々とした雑貨の買い物に便利です。また、美味しいパン屋さんやお弁当屋さん、クリーニング店なども、近くにあると生活が豊かになります。
物件を中心に、どのようなお店が徒歩圏内に揃っているのかを地図アプリなどで確認し、実際に街を歩いてみることで、その場所での具体的な生活をイメージしやすくなるでしょう。
まとめ:一人暮らしでスーパーの距離が遠い問題は工夫で解決!
今回の記事のまとめです。
- スーパーまでの理想的な距離は多くの人が目安とする徒歩10分以内
- 物件の内見時は必ず自分の足でスーパーまでの道のりを確認する
- 自転車やカーシェアを上手に活用して移動の負担をぐっと軽くする
- 計画的なまとめ買いと食材の冷凍保存で買い物の頻度を最適化する
- お米や飲料など重くてかさばる商品はネットスーパーで注文しよう
- スーパーだけでなくコンビニやドラッグストアも買い物先に含めてみる
- キャリーカートやリュックを使い荷物を運ぶ身体への負担を減らす
この記事では、一人暮らしでスーパーが遠いという悩みについて、理想的なスーパーまでの距離から、遠い場合の具体的な対策、さらには物件選びのポイントまで詳しく解説してきました。
まとめ買いや冷凍術を駆使したり、ネットスーパーや食材宅配といった便利なサービスを上手に活用したりすることで、スーパーが遠いという物理的なデメリットはカバーできます。
これから部屋を探す場合は、今回の記事で紹介したポイントを参考に、後悔のない物件選びをしてください。自分に合った最適な方法を見つけて、毎日の買い物をより快適なものに変えましょう。